風のむこうがわ|1967 初夏ーある日のスケッチー|ピキと少年
J
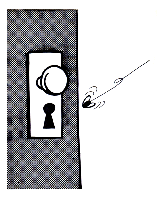
ピキは、いつか少年が話してくれた、神さまのことを思いました。小さな手を合わせてお祈りをします。
「神さま、お願いです。ボクは、このまま死んでもかまいません。その代わり、大好きな少年の家を火事にしないでください」。
何べんくり返したでしょう。突然、バキッと音がしました。警報器のプラスチックのカバーが破れました。警報器の前を通った車が石ころをはね、それが当たってくれたのです。しかし、警報器のボタンは押されておりません。ピキは、もう一度、神さまにうかがうように夜空を見上げました。凍るような寒さのため、もう呼吸することも苦しくなっていました。
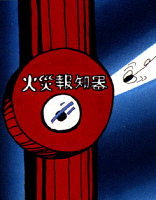
空にまたたく星が、流れる雲に見えかくれしながら、何か語りかけているようです。でも、ピキにはもう聴きとれなくなっていました。一きわ、強い光を放って輝いている星は、オリオンでしょうか。ピキは少年の理科の本でその星座の位置も確かに見おぼえています。
「理科、そうだ。理科の教科書にはスイッチが載っていた」。スイッチの実験があったのです。神様に心から感謝のありがとうを言いました。警報器のところまで一息に舞い上がろうとしましたが、冷たい地面におりていたので羽根は冷えきってかたくなり、動きません。ピキはあせりました。こうしている間にもおそらく火は燃えひろがっているでしょう。ピキは必死です。冷たく重くなった体をひきずるようにして、スイッチボタンのカバーまで、なんとかはい上がりました。
割れてギザギザになっているふちに手あしが、かかったではありませんか。スイッチボタンは押さなくともボタンと接触するスイッチ本体とつながりさえすれば、電流が流れ、ベルは鳴る筈です。
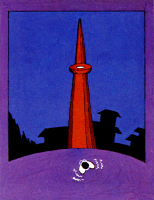
K
ピキは、スイッチボタンの中へ入りこみました。自分の体に電流を流すことに心を決めたのです。「電流が流れるものは、ドウタイ(導体)だったね。ボクはドウタイになるよ」。
そのままでは、体がとどきません。寒さに動かない羽根を精一杯力をこめてひろげました。羽根が一杯に開ききる時、ピキの体はドウタイになるのです。
ピキの眼に涙がうかびました。その涙はみるみるもり上がり、溢れ出しました。やさしかった少年に「さようなら」を言いました。足とうででしっかり体を固定して残る力をふりしぼり、おとろえる気力をふるい立たせ、羽根の先が破れよとばかり開きました。羽根についた霜や流れる涙が電気の流れをよくしたのでしょう。
ギューン、ビビビィ。警報器が夜の闇をきりさいて鳴りひびきました。
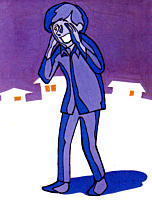
L
少年は、ねむい眼をこすりながら、ボヤですんだ勉強部屋に立っております。そして、あちらこちら探しました。もちろんピキをです。しかし、どこにも見えません。棚の隅の小さなベッドはからっぽです。
「この火事さわぎで、どこかへいってしまったのかな」。少年は大切な友達を失ったように急にさみしく、不安になりました。思わず、「ピキッ、ピキーッ」大声で叫びました。まだ、ざわめいている夜の町に、少年のピキを呼ぶ声が聴こえます。その叫び声に重なるように、どこかで、「警報器で知らせてくれた人はおりませんか」………。
11時56分、あと4分ほどで、新しい年がやってくるという時刻でした。
このサイトは、有限会社スターシップ・コーポレーションが運営・管理しています。
Copyright © 2007 Starship・corporation. All Rights Reserved.

